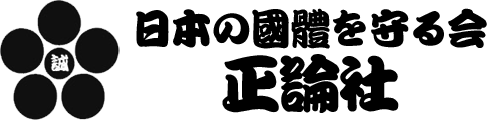【差別と部落 其の弐】穢 kegare
黄泉の汚穢
古代・中世・近世を通して被差別観の根源である卑賤視と忌避意識は形は変わっても常に存在していた。
上古の神々の時代から日本人は死を恐怖し忌み嫌い、死を穢れと考えていた。
黄泉の国に向かった伊邪那岐命は妻伊邪那美の腐乱し膿沸き蛆虫蠢く悍ましい姿を見てて逃げ還られたという異郷訪問譚の神話は有名であり、本居宣長は「古事記伝」で穢れの起源をその「黄泉の汚穢」と論じている。
大国主命の子の阿遅鉏高彦根命も葬儀に訪れた時に死者に間違えられ怒り狂い「何とて吾れを穢き死人に比ぶるぞ」と剣を抜き喪屋を切り倒し死体をけとばしたと云うほど死を忌み嫌ったという。

神聖観念と不浄観念
「穢」は本来宗教的な神聖観念(霊力・呪力・威力)の一つでもあるが、罪や災いと共に日本古代の不浄・罪穢観を表している。
忌または服忌を記紀では穢・汚・汚垢・汚穢・穢悪などと表記され、「ケガラワシ」とも「キタナシ」とも読まれている。
災いが起こる原因「罪」と「死」とに繋がる不浄なモノが「穢」なのである。
英国の文化人類学者メアリー・ダグラス(Mary Douglas)は汚穢概念(pollution)について「絶対的汚物といったものはあり得ず、汚物とはそれを視る者の眼の中に存在するにすぎない」と論じている。

朝廷祭祀と触穢観念
朝廷祭祀に於ける穢れについては、平安初期に編纂・施行された基本法典「弘仁式(弘仁11年 820年)」「貞観式(貞観13年 871年)」から受け継がれた「延喜式(延長5年 927年)」で穢れ観念と行動規範の基準が成立した。
その「穢」を考察すると、死穢・産穢(荒忌)・胎傷穢(死産)・血穢・六畜の死穢産穢・失火穢があり、具体的内容と触穢の定義を定め行動規範を示している。
観念的な触穢、「ケガレ」と「キヨメ」の都市構造が天皇を中心として構築されていったのではないであろうか。

払拭できない「穢の者たち」
死穢をキヨメめ罪穢を祓う儀礼「修祓」がある。
服忌のとき禊ぎによって清浄な体に浄め、祓えによって悪疫退散祈願と心の不浄を清める浄化の所作をするのである。
しかし、服忌によっても禊祓によっても払拭できない「穢」の者たちが存在する。
漢字の中で「穢」という字ほどイメージ的に呪われた文字はない。
広辞苑では「身に接し目に触れ、器物衣食に及ぼす一切の不浄をいう」とあり、けがれ・きたない・わるいと散々である。
その文字から生まれた「穢多」という同情なき侮蔑の名称は呪われている。
「穢多」は「エタ Eta」と読まれているが、 文字を離れての呼ぶ場合の通称は「エッタ Etta」である。
「穢多」という文字が累をなして、世の中の人から理由も知られずにただ穢(汚)ないものだと盲信せられ続けた事実は哀しい。
更に、非人は足洗をして平民になる道もあったが、「エタ」は人そのものが 穢れているからと足洗は絶対に出来なかったのだから生れ落ちたら逃れる術のない非情なる絶望の境遇である。
「穢多非人」の称は明治四年に廃せられたので、それより後「エタ」なるモノは法的に存在はしない筈であるが・・・
穢れの観念をめぐっては時代の推移と変化そして社会的背景の相違に注意する必要があるが、人心に住む差別の心の闇は今も消えない。
大墓公阿弖流為之末裔