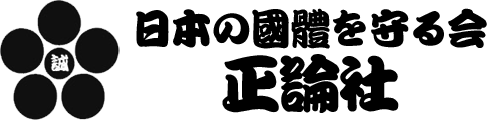高山彦九郎先生所縁の地を訪ねて
維新魁の志士 高山彦九郎先生。
延享4年5月8日(1747年6月15日) - 寛政5年6月28日(1793年8月4日)幕末、維新の志士達に大きな影響を与えた、尊皇運動の先駆者である。

赤城山 真白に積もる 雪なれば
我が故郷ぞ寒からめやも

幕末、維新の志士達に大きな影響を与えた、尊皇運動の先駆者である高山彦九郎正之(字仲縄)先生。
彦九郎翁は、自らの尊皇思想を練り上げ、日本中に皇権復活「建武未遂の偉業の完遂」と復古神道の精神(日本民族固有の精神)を伝播した維新魁の志士である。林子平、蒲生君平と共に 寛政の三奇人と云われた。
寛政2年、江戸滞在中の彦九郎翁は奥羽・蝦夷地を単身訪ねる決心をし、房総から津軽三厩を目指す長い旅にでた。途中、水戸で藤田幽谷・立原翠軒・木村謙次等と、米沢では莅戸太華等と、仙台では林子平と、各地で多くの人々と対談している。津軽に至りはしたが、海峡越えは難しく蝦夷地を断念し、光格天皇の新皇居還幸の儀式見学の為、京に急行した。
そして、師走に京の地に舞戻った彦九郎翁に人生最大の喜びの時が訪れたのである。
草莽一介の身を以て、その名が今上天皇の叡聞に達するを聞き、感激は頂点に達したのであった。

われをわれと しろしめすかや すべらぎの
玉の御こえの かかるうれしさ
《歌意》
微賤なる草深い田舎侍の私を、高山彦九郎と思召し、親く玉音をお与えいただき、これはまた何という破格の光栄で、畏れ多いことであろう。
※すべらぎ…天皇のこと ※玉の御聲…天皇のお声がけ
この時の事情は、「近世日本國民史(徳富蘇峰著)」の文によれば、琵琶湖で漁師が珍しい萬歳緑毛亀(蓑亀・藻の付着した亀)を生捕り、評判を聞きつけた彦九郎翁が買い取り、侍従であった伏原宣条卿を経て「亀に毛あるものは文治の前兆なるが故」との言い伝えから御叡覽に供するに至つた様である。
彦九郎翁は、この亀を一生の宝物として修正持ち歩いたそうで、終焉の地福岡県久留米市の真言宗遍昭院に遺品の一つとして遺されているそうである。




光格天皇と尊号一件
後桃園天皇の養子として即位した光格天皇は実父典仁親王に対して太上天皇(上皇)の尊号を贈ろうとしたが、不遜にも老中・松平定信が「皇統を継がない者で尊号を受けるのは皇位を私するもの」として反対したことで「尊号一件」が起こり朝廷は敗北し、幕府に追い詰められた。
彦九郎翁は狂気と失意の中、辞世の句を残して寛政5年6月28日に自刃した。
朽ち果てて 躬は土となり墓なくも
心は国を守らんものを

彦九郎翁憤死後、時は経ち明治維新を成就させた勤皇の志士達は、私心なき純潔の行動者であった彦九郎翁に深い感銘を受け心の鑑と仰いだのであった。
幕末期の歌人・橘曙覽による和歌
大御門その方向きて橋の上に
頂根突きけむ真心たふと
《歌意》
皇居の方向へ向つて三條大橋の上から、額を着かんばかりに望拜してゐる「眞心」の何と尊いことであらうか。
橘曙覽は「源実朝以後、歌人の名に値するものは橘曙覧ただ一人」と正岡子規も絶賛した人物である。
明治の中頃の俚謡、サノサ節には、
人は武士 気概は高山彦九郎 京の三条の橋の上
遥かに皇居をネ伏し拝み 落つる涙は鴨の水アサノサ
と謡いつがれたと京都市観光部振興課 高山彦九郎大人 顕彰会は記している。
久留米の真木和泉守も哀悼の歌を捧げている。
新らしと 人は言わねども 春はただ
古き神世に 立ちかへるらむ
吉田松陰先生。通称は「寅次郎」。諱は「矩方(のりかた)」。
字は義卿、号は「松陰」の他、「二十一回猛士」。
「松陰」の号は有名であるが、それは尊敬していた高山彦九郎翁の諡(おくりな)「松陰以白居士」からとったものだと言われている。

そして松陰先生の辞世の句「躬はたとい武蔵野の野邊に朽ちぬとも 留め置かまし大和魂」は、彦九郎翁の辞世「朽ち果てて躬は土となり墓なくも 心は国を守らんものを」の本歌取りであろうか。
西郷隆盛翁も文久2年末、沖永良部島に幽閉中、彦九郎翁の激烈なる尊皇心をたたえる詩文を詠んでいる。
精忠純孝群倫に冠たり。
豪傑の風姿画図に真なり叵し。
小盗謄驚くは何ぞ恠しむに足らんや。
回天業を創むるは是れ斯の人。

大墓公阿弖利爲の末裔