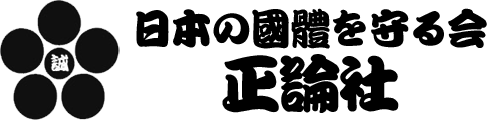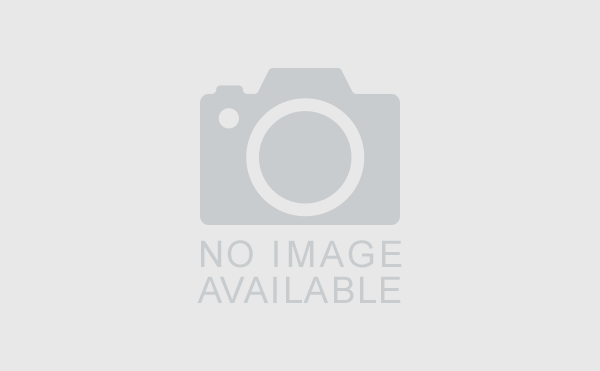秩父路を往く(壱) 高山不動尊
秩父路を往く(壱) 高山不動尊


武蔵の高幡不動、下総の成田不動と並んで「関東三大不動」の一つに数えられる奥武蔵の名刹が高山不動尊、正式名は「高貴山常楽院」
創建は654(白雉5年)という古刹で、往時は標高600mという奥武蔵の山中に36坊を持つ修験道場として隆盛を極めていたそうである。
明治維新の廃仏毀釈・神仏分離で、真言宗智山派となる。
伝承よる寺伝では、716(霊亀2年)に行基が五大明王像(不動明王・降世明王・軍荼利明王・大威徳明王・金剛夜叉明王)を自刻したというが現存する本尊・木造軍荼利明王立像は平安中期の作と推定されている。
鎌倉期から戦国時代にかけて武将たちは厄難除災と煩悩を断ち切る為、不動明王を信仰した。この古刹も源頼朝・足利義政・徳川家康などの権力者から尊崇を集めたそうである。
その名残を留める本堂(再建1849 嘉永2年)は豪壮な唐破風造りである。

桓武平氏の坂東平氏系一門で鎮守府将軍・平良文の孫である平将恒とを祖と平将門の次女春姫の長男の忠常は千葉氏の祖、次男の将恒は秩父氏の祖、三男の頼尊は中村氏(末に相馬氏)。秩父重綱の子重遠が高山氏を称した。高山党は高麗郡を拠点とし木曽義仲が挙兵に呼応し信濃で戦っている。
そして、戦国時代まで高山党は健在で国人領主として命脈を保っていたが小田原征伐で後北条氏と共に没落した。
神祠歴拝居士




の軍荼利明王さま.jpg?resize=619%2C1013&ssl=1)


【所在地】埼玉県飯能市高山346
【文化財】
重要文化財 木造軍荼利明王立像
県指定文化財 常楽院不動堂
不動明王像
市指定文化財 無間鐘
県指定天然記念物 大イチョウ 推定樹齢800年